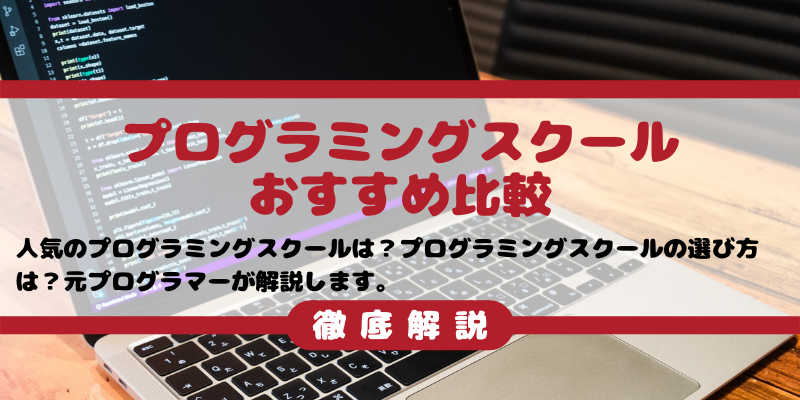英語を学習するといっても、いろいろあります。
リーディング、リスニング、スピーキング、ライティング。
それぞれが大事ですが、ここでポイントなのが、その学習順序です。
一般的な英語学習でいうと、リーディングから入ります。
最近の子供の英語学習を見ていると若干違うようですが、それでも基本的には英文を和訳するリーディングが主体なのは間違いなさそうです。
ところが、言葉というのは音で成り立っているんです。これが私の持論。
言語は音の世界だ!
今でこそあまりいませんが文字が読めない人は存在します。
しかし、そのような人たちでも会話は成立します。
それは言葉は音でやりとりするからにほかなりません。
読む・書くという行為は音と文字を変換しているだけに過ぎないのです。この文字を音に変換ができるか否かが、文字を読めるか読めないかの違いです。
子供が言葉を学ぶ順番としては、まずはリスニング、そしてスピーキングが行われます。
この後に本を読んだりしてリーディングを学び、最終的にライティングもできるようになります。
日本語で考えれば、読める漢字なのに書けないことはよくあることだし、書く行為は一番後回しです。文章を書くのが苦手という人はいくらでもいます。
もちろん、この学ぶ順序というのはあくまでも、どっちが先かを考えた結果であり、実際には同時並行で行われます。
リスニングが完璧になってからスピーキングに行くわけではなく、まず最初にある程度のリスニングでインプットをして少しずつアウトプットし始めるのです。
全てが同時進行していくわけですが、どれが一番先行しているかと考えれば、恐らくリスニングだろうと思うのです。
赤ちゃんは2歳頃までは聞くことに徹しています。
なぜなら、聞こえない音は発音できないし、発音できない音は聞こえない。
しかし、厳密に言うと発音できない音は聴き分けにくい。聴き分けにくいが頑張れば多少は聴き分けられるので、じっくり耳を傾けて聴き、聞こえた音を発声してみることを繰り返していくと次第に聴き分けられるようになる筈なのです。
従って、英語学習において、まず最初にやらなくてはならないのは英語の音に耳を慣らすこと、そして、口や舌を慣らすことの筈なのです。
全ての発音記号の音を聴きわけ、そして発音できるようになることが最優先事項だ!と言い切ってしまいます。
この時に、やりがちな間違った方法は聞き流すこと。
残念ながら聞き流していては、耳は日本語の周波数から抜け出せません。
何かをしながらは聞き流しではダメなのです。聞き流すのでなくて、じっくり聴かなくてはなりません。
私自身、散歩しながら、ランニングしながら英語の音声を聞いていたことがあります。半年ほど続けてみましたが全く効果がありませんでした。
一応、自分では意識を耳に置いていたつもりではあるけど、やはり中途半端なのでしょう。
こういう聞き流しは、耳が慣れてしまった後、英語の発音が聴き分けられるようになってから行うべきで、初期の段階では絶対にやってはならない時間の無駄だと思われます。
しかもこの方法の悪いところは勉強している感があるのです。
勉強しているのに成果が出ないという何とも言い難い気持ちになるのですが、そもそも無駄なことをやってるのだから成果が出るわけがないのです。
リーディングは音への変換
ところで、皆さんが本を読むときは、黙読をしますか?それとも音読をしますか?
子供が最初に本を読むときは音読が多いように思いますが、大人は黙読していることが殆どでしょう。
そう、黙読するんです。
黙読というと、どうやって読むかというと、頭の中で文字を音声に変換して理解しています。
速読をする人は文字をそのまま理解できるようですがほとんどの人は一度音声に変換してから理解しているはずなのです。
私など、どういうわけか音読をするとほとんど意味が分からなくなります。
発音することに意識がいきすぎて頭に意味が入ってこないようなのです。だからといって黙読で音声変換せずに読もうとしても全く意味が頭に入ってきません。
例えば、I study English.という英文。
このとき、私たちは「アイ、スタディ、イングリッシュ」と読みます。
さすがにこの程度の英文だと、これでだいたい意味が分かりますが、もうちょっと複雑な英文だとすると、この次に和訳をします。
このとき「私は、勉強する、英語を」という日本語の音に変換する。
ここでポイントなのは音に変換しているという点です。恐らく日本語の文字に変換して考えている人はいない筈です。
すなわち、言葉は音で理解するのです。
ここでは、和訳をしましたが、本来は、I study English. という音のまま理解できるようになりたいのです。
もし、Englishという単語の意味が分からないのなら、そのときにだけ日本語と紐付けて「英語」という音を引っ張ってくればいい。
当たり前ですが、音の世界なのだから諸行無常です。後戻りして考えている暇はありません。聞こえた音をそのまま理解していくようになるのが言語の学習なのです。
それは、リーディングでも同じことです。文字を読むということは文字を音に変換して理解しているのだから、英語の音を理解できる脳がなくてはなりません。それ以前に、文字を音に変換する必要があります。
逆に考えれば、もしあなたが速読で英語を読もうとしているのであれば、音をすっ飛ばしてもいいのかもしれません。
私は速読ができないので文字で意味を認識できるのかはよく分かりませんが、日本語の文字を音変換しなくても理解できるのなら、英語だって文字だけで認識できるはずです。
ならば、音を学ばずに文字で意味を理解する学習をした方が手っ取り早いのかもしれません。
しかし、もし速読ではなく、普通に聴き、話し、読み、書くことをしたいのなら、まずは英語の音を理解する学習をすべきだろう!というのが私の結論です。
まとめると、英語を話す声の音を聞きとれるようになるのが第一段階。
そして、聞こえた音のまま理解できるようになるのが第二段階です。
次に文字を英語の音に変換する、言い換えれば音読できるようになるのがリーディングで、これは英語の音声を理解できた後の話で、第三段階です。
間違ってはいけないのが、これらはそれぞれを順番に繰り返し行い、次第に難しい英文に対応していくという点です。
第二段階で難しい英文の意味が理解できるようになるまで音読をしないということではありません。
英語脳とか英語回路とか
英語脳というとなんだからそれっぽいですが、別にどうってことはありません。
単に英語の音を音のまま認識できるだけの話です。
日本語と英語は文法が全く違うから難しいといわれることもありますが、それは文字情報から理解しようとするからそう感じるだけで、音の世界ではどうでもいいんです。
文法は英語学習する上では学んだ方がいいのは間違いありませんが、文法はあくまでも後付けの概念です。
少なくとも私は、日本語の文法なんてほとんど知りません。学校で多少学んだとは思うのですが、たぶん大して理解はしていないし、そもそも全く覚えていません。
自分の子供が、五段活用がどうとか言ってるのを聞いても遙か遠い昔に聞いた記憶があるだけで、それが日本語の文章を組み立てる上で役立つことはなさそうです。少なくとも知らなくても何とかなっています。
だから、英語の文法も知らなくても問題ない筈です。もちろん、外国語はネイティブほどのインプットが得られないので、それを補完するという意味で文法を知っていれば役立つでしょう。
どなたかの本で文法は地図のようなものだと書かれていましたが、だいたいそんなイメージだと思います。どこかに行くのに地図はなくても行けることは多いでしょうが、迷ったら地図を見た方が早いです。
でも地図の見方が分からなかったら意味がない。だから文法は学んでおいて損はないのです。
しかし、補完するだけの話です。
そもそもネイティブの多くは文法を理解していないだろうし、間違った文法の言葉も沢山ある筈です。SNSなどで書かれている文章を文法を元に解読しようとしても難しい可能性はありそうです。
だから文法ばかりを頼りにすると、意味を間違えてしまう可能性もありますし、文法は変化していくものでもあります。
それでも、本を読んだりする場合は、そういうリスクはかなり低いだろう(文法的におかしな文章は修正されているだろうと思われる)し、文法を駆使して間違わないように読まなくてはならない文章(ようするに学者が書きそうな難解な文章)なら明らかな文法間違いの英文である可能性は低いだろうとも思います。
話がそれましたが、英語は、というより言語は音の世界に存在するんだということを忘れてはなりません。
文字は、音を具現化しただけに過ぎなくてあってもなくてもいい存在なのです。
英文の音声を聴き、そのまま頭に意味が染みこんでくるようになるのが、英語脳とか英語回路とか呼ばれるものです。これができるようになれば、とりあえずの英語の学習は完了です。
これ以降は、語彙力を高めたり、文章力を鍛えたり、試験勉強したりと、英語がどうのこうのということではなくなってきます。
幼児並の英語力でいいのか、大学教授や政治家のようになりたいのかだけの話で、これは継続的なインプットでなされる部分です。
従って、英語学習、言語学習をするのなら、まずは音として英語(言語)を学習するところから始めるべきなのです。
この点をおざなりにしているから日本人の英語学習は失敗することが多いのではないのか・・・と思うのです。